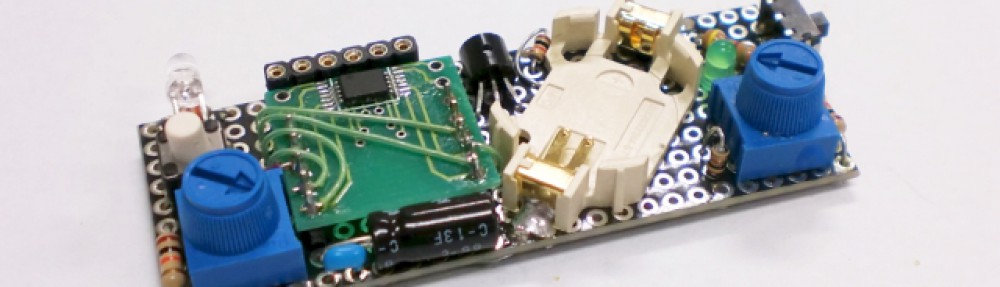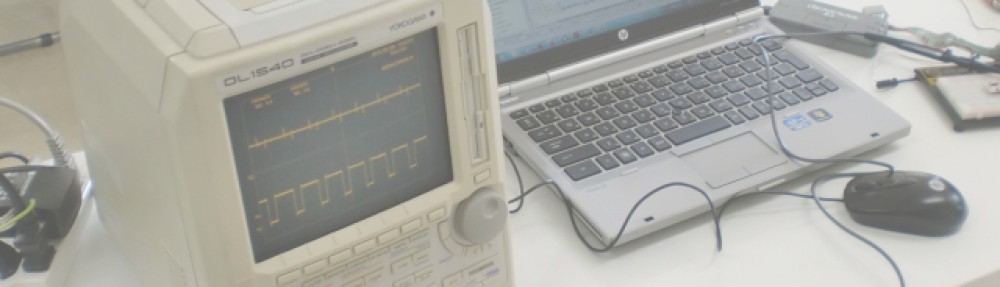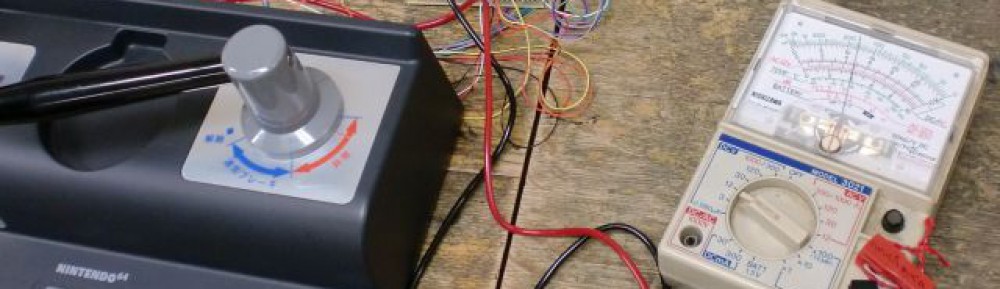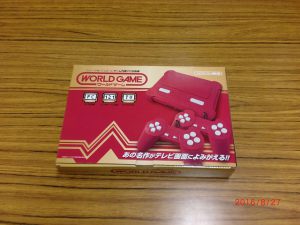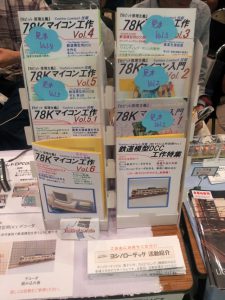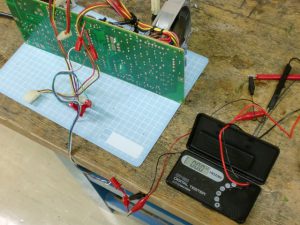前回までメンバー個々の事情・コミケの準備(主に記事書き)でバタバタしていた反動でしょうか、今週のローテクは「ゆる~く」活動となりました。
まずは私(マサ)の活動報告です。
仕事で月一の本社打合せの帰りにアキバへ寄り、IchigoJam(イチゴジャム)を購入しました。
・・・コレで3台目です。

パーツはこれだけ。
うちの甥っ子どもがもう少し大きくなったら勧めてみよかしら?
(妹弟に殴り○されそうだ・・・)

コレで完成。あとはテレビにつなげるだけでBASICがつかえるんだから大したもんです。
続いてあーさんの活動報告。
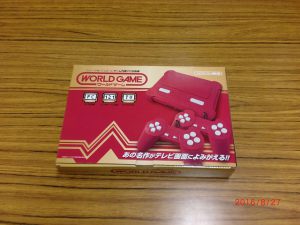

酔った勢いでゲーセンのクレーンゲームでGetしたそうな。
FC互換機です、内蔵ゲームも121個あるそうです・・・大半のゲームは意味不明だそうな(マニュアル・取説なし)
本体は本家FCとは比べモンにならないくらい貧弱なプラスチック筐体でした。

ROMカセットを挿さないと内蔵ゲームのメニューが立ち上がります。
私もいくつかゲームをやらせていただきましたが、やはり意味不明でした。
写真はありませんが、途中、スー○ーマ○オ3のROMカセットを挿しプチゲーム大会となったのは秘密です。
裏ワザ合戦(?)となったのも秘密です・・・メンバー曰く「頭が覚えていなくても体が覚えている」とのこと。
最後に
高校在学時お世話になった(私の記憶では進路指導だった)先生がローテクに持ってきてくださったモノの御紹介を。
(当日、先生は別の用件でローテクに用がおありでした)

ピーナッツかぼちゃと言うそうな。
「調理して残った種使えるよ」と言われましたので、早速来年畑に植えてみます。
(M)